 |
2003/09/06 |
9月に入り少しずつ遠ざかり始めた火星です。中央付近に大きな黒い点のように見えるあたりが
ソリス平原になります。この黒い点は太陽湖とも呼ばれる火星を代表する地域のひとつのようです。
この部分は時間とともに変化していることが観測されています。右下には太陽系最大の火山、
オリンポス山があります(写ってないですけどね)。その高さはなんと24000mにもなるそうです。
|
 |
2003/08/28 |
最接近1日後の火星です。ホワイトバランスを電球で撮影したため色合いが前回とは異なります。
最接近時の地球と火星の中心距離は約5576万キロ。軌道の中心がずれている火星との接近時の距離は約5500
万キロ〜1億キロと倍近く異なります。今回以上の大接近が起こったのはなんと6万年前になります。
次にこれ以上の大接近が起こるのは2287年になります。
|
 |
2003/08/26 |
最接近前日の火星です。視直径が25.1秒角あります。8/2の画像に比べて南極冠が小さくなっています。
これは火星の南半球が夏に向かっていることを意味しています。白い部分は氷なのですが、水ではなく
二酸化炭素が凍ったものだと言われています。成分的にはドライアイスと同じようです。
|
 |
2003/08/02 |
2003/08/27に最接近する火星です。現在の視直径が22.6秒角あります。2年前の大接近と言われたとき
でも最大で20.8秒角ですのですでにそれ以上の大きさです。今回の最接近では25.13秒角になります。
|
 |
2003/01/12 |
同じくMeade LX90-20で撮影した木星です。高度が低いためあまり鮮明ではありませんが大赤斑
が確認できます。最近は赤みが薄いため、眼視では確認することができませんでした。
|
 |
2003/01/12 |
Meade LX90-20で撮影した土星です。眼視ではもっとはっきりとカッシニの空隙が確認できたように
思います。この写真でもわずかに空隙を確認できるようです。この光学系は屈折式に比べると
像が甘いといわれていますが、鏡筒を充分に冷却し筒内気流が乱れないようにすれば口径差が
生きてくるように思えます。
|
 |
2002/11/20 |
この夜は月に暈(かさ)がかかって見えました。C-2020ZOOMの広角よりでも画角に収まらず、
Kenko DEGITAL SEMI FISH-EYE 0.45xを使用しています。完全にけられていますが、かなりの
広範囲が撮影可能です。価格も安いので遊ぶには面白いですが、レンズが暗いので16秒しか
露出できないC-2020ZOOMで天体撮影に使用するのは難しいかもしれません。1等星の多い
冬の空でテストして見たいと思います。
|
 |
2002/11/02 |
昼間に見える月です。明け方の空に見えるはずですが昼間でもよく探せば見つけることが
できます。この時期は空が暗いうちに露出をかければ地球照(earthshine)がきれいに写る
はずです。
|
 |
2002/10/11〜2002/10/18 |
10/11から10/18までの8日間の太陽面をアニメーションGIFにしてみました(329KB)。CAMEDIA C-2100
にx1.8テレコン、ND400x2での撮影です。これから活動が低下していく(11年周期)とはいえ、まだ大きな黒点が
発生している様子が見えます。
|
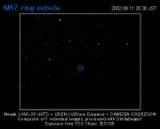 |
2002/08/11 |
こと座にあるリング星雲M57です。明るさは9.7等と明るくないのですが、視直径が小さい為、単位
あたりの輝度が高く写りやすいようです。眼視でもリングが確認できました。LX90-20での
ファーストライトになります。夏なので気温が高くノイズがのりやすかったので、使えるのは
これ1枚でした。それでも口径のおかげかここまで写っています。これからが楽しみです。
|


